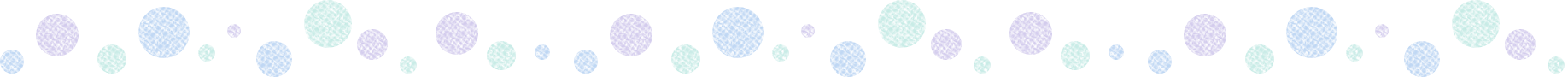身近な人、大切な人を自死・自殺で亡くされた方が、胸のうちを綴られました。
出典の記してあるものについては、もとの文章のごく一部しか掲載されておりません。折をみて、ぜひ全文をお読みいただければと思います。
*手記の全部または一部の無断転載は固くお断りします。
真実を伝えるということ
齋藤香さん
夫が亡くなったのは2008年夏。当時夫は45歳、私43歳、長男13歳、次男2歳半でした。
長男は、夫が行方不明から死亡した経緯で自殺と理解しましたが、幼い次男は父親の死さえ理解出来ず、遺骨の帰宅に「おかえり…」と声をかける私に「パパいないよー」と部屋中を捜し続けていました。今でもその様子を思い返すと胸が締めつけられます。
夫が亡くなった当時は手続きなどでとても忙しかったのですが、何をしたのか、どのように過ごしていたのか、全く憶えていません。ただ、人に会うことにひどく緊張していた筈なのに平静を装っていたような気がします。
長男は「ママは死なないよね?」と、とても不安そうでした。けれど「三人になっちゃったけど頑張ろうよ」と私を励ましてくれたり、「疲れてる?大丈夫?」と気遣ってくれたりしていました。生活のことなど不安でいっぱいでしたが、そんな長男の気遣いに、先の事まで考え過ぎず今目の前にあることに向き合おうと努力したつもりです。
長男とは夫についてたくさん語り合いました。でも、理解しているとはいえまだ中学生。本当に辛かったと思います。次男にはどのように真実を伝えたらよいか、ずっと考え続けていました。まだ就学前です。でも当然、「パパはどうしてなくなったの?」と質問してきます。
嘘はつきたくない。「突然心臓が止まってしまったのよ」とだけ答えていました。
保育園ではお友だちから「キミのパパしんだの?」と訊かれ「ボクのパパはなくなったの。とてもかなしいことなんだよ!」と答えていました。その場に居合わせた私は気持ちが強張って何も言えませんでしたが、ちゃんと気持ちを言葉に表せる次男にとても驚きました。
でも私には「ボクはさみしくないよ。おにいちゃんもいるし、ぜんぜんさみしくないよ。ママがだいすきだから。ママのごはんおいしいから!」と一生懸命慰めてくれるのです。
真実を話すのはまだ先であるにしても、日頃から何か訊かれたときには何事も正直に応えることが大切なのではないかとその時思いました。
次男は父親のことが殆ど記憶にないので、写真やビデオを一緒に見ながらその姿を探しました。どんな風に喋っていたのか、こんな時はどうしていたのか、今だったらパパはどんな風に考えるだろうか…。
分かちあいや子どものつどいでお世話になっている全国自死遺族総合支援センターのスタッフの方々の支えもあって次男に真実を告げたのは、彼が9歳の時です。思春期に入る前にどうしても話しておきたいと思っていました。
いつものように三人で食事をしながら夫の話題になった時、何故だか「あっ、今だ!」と思う瞬間があり話し始めました。同時に夫から次男への手紙も渡しました。
とても驚いた様子で手紙を読み、しばらく自室に籠っていましたが、程なく出てきて涙をポロポロこぼしながらこう言ったのです。「パパと結婚しなければママがこんなに苦しまなくて済んだのに…」
子どもってそんなふうに考えるのですね。私はどうしてパパを止められなかったのかと責められても仕方ないと思っていました。「パパと結婚したからあなたたちと出会えたのよ」そう返しました。
真実を告げたことで終わりではなく、大切なのはこれからだと感じました。長男に対しても同様ですが、夫のことだけでなくいつでもどのような事でも常に正直に向き合う。お互いの気持ちを受け入れて話し合える間柄が大切なのではないかと更に強く思ったのです。
しばらくは次男の葛藤の日々が続きました。「なぜ自分で命をなくしてしまったのか。なぜもっと一緒にいてくれなかったのか。ボクたちのことは大切ではなかったのか…」
このような時期はとても心配ではあったけれど、彼の成長の段階と捉えその時間を大切にしようと心がけました。その後、少しずつ気持ちが落ち着いてきたようで、今では父親への憧れも言葉で表現出来るようになりました。
子どもたちの学校へは私から正直にお話しました。先生はとても緊張なさったと思います。他の先生方と情報を共有していただき、「特別扱いする必要はなく、何か少しでも変化があったなら連絡して欲しい」とだけお願いしました。次男は毎日帰宅すると、「今日は○○先生が話しかけてくれたよ!」と嬉しそうに報告してくれました。先生方が代わるがわる何気ない言葉かけをして下さったのは本当に有り難いことでした。
温かく見守っていただき、子どもたちはそれぞれ感謝の気持ちを持って卒業しました。
現在、長男は社会人として独立し、次男は将来への希望を胸に学生生活を送っています。今では二人とも私の良き相談相手となってくれて、とても頼りになります。
子どもたちがいなかったら夫の死にフタをして私は何も語らなかったことでしょう。彼らは親を失ってとても辛い。言葉になんて表せないほどだと思います。そんな中でも、親が子どもたちを想うよりもっと、彼らは残された親を気遣っているのです。お父さんお母さんに笑顔でいて欲しいと必死なのです。つどいに通うどのお子さんを見てもそう確信します。
親が自殺で亡くなったことを引け目に感じて生きていてはいけない。その死をもって生きる意味を深く考えて欲しい。また、夫は命を粗末にしたのではなく、子どもたちを想って精一杯生きたのだということも私は伝えたいのです。この先、子どもたちが自己肯定感を持ってしっかりと前を向いて歩み生きていくために、真実を伝え夫の死を一緒に考えることは最も重要なことではないかと私は思うのです。
今までも、そしてこれからもこれ以上の不安を与えないように心がけ、出来る限り温かい食事を一緒に摂り身体を休めることに努め、毎日子どもたちにとってひとつでも多く「いいこと」がありますよう願っています。
夫はとても手のかかる幼な子のような人でした。私が息子に添い寝をしていると舌打ちをするほど焼きもちやきでした。誰よりもだれよりも自分が一番に愛されたかったのでしょう。人は愛された記憶を糧に成長していく。満たされない気持ちはやがて自分や他人を傷つけてしまうということを夫は教えてくれたのです。
けれども、私はそんな夫の思いの深さに気づくことが出来ず、夫の幼稚さに呆れ「大人なのになぜ?」と蔑む気持ちさえありました。今は悲しみと共に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、果たして私はどうすれば良かったのか今でもわかりません。この先も一生、自問自答を繰り返しながら子どもたちと共に歩んでいきたいと思います。
-日出美ちゃんごめんねありがとうね-
あなたが亡くなって4年2ヵ月が経ちました
仰木奈那子(針馬ナナ子)さん
日出美ちゃんが逝った直後から重いうつ状態となり、1年後には指示通り飲んだ薬のせいで朦朧となって家の階段から2度も落ち、右膝下を7針、頭を24針縫う怪我をしました。それからすぐに歩けなくなり、パーキンソン症候群と診断されて介護保険を受けました。さらに脊椎側湾症にもなって、おかあさんの心の傷は肉体の傷となって表れ、天罰が下されたかのような日々が続きました。苦悩する日出美ちゃんに寄り添わず、批判ばかりした自分を責め続け、ついには泣くこともできなくなりました。
歩くこともできず涙も出ない苦しみの中、死にたいと思う一方で、今死んでも罪深いわたしは日出美ちゃんの居るところへは行けない、死んでも会えないのならばどんなに苦しくても生きて、あなたの写真に詫びよう、ビデオで生きている姿を見よう、短歌で生きた証を残そう、そう思ってやっと生きていました。
半年が経った頃、春秋のお彼岸に、亡き人に宛てた手紙をお焚きあげしてくださるお寺があることを知り、その日から毎日便箋一枚の手紙を書き続けています。もう3年9ヵ月ほどになるので、1300枚あまりの「ごめんねありがとうね」がお焚きあげの煙となって日出美ちゃんの許に届いたことでしょう。手紙を書くことで毎日あなたとお話しできるし、傍にいてくれることが信じられるようになりましたよ。
2017年秋頃から、泣くことも歩くこともできるようになりましたので、日出美ちゃんの勤務先だった病院、二人で食事したレストランや遊びに行ったところを訪ねるようになりました。そこにあなたの生きた証があることを確かめたかったのです。これをあなたと同行二人のお遍路旅と思うことにしました。一人きりになってしまったおかあさんには、日出美ちゃんとの思い出の場所こそ幸せがあった場所だから、その場所を訪ねるたびに幸せを重ねてゆくのだと思うことにしました。9ヵ月ほど歩けなくなった時期があったので、自由に歩けるありがたさが身に染みます。
今年4月、わかちあいのスタッフの方々から支えていただきながら自分もスタッフとなって、人さまと積極的に関わろうとしています。日出美ちゃんが居た頃は一人で居ることが好きなわたしでしたから、今のおかあさんを見て「変わったなあ」と思っているでしょうね。
また、要約筆記者の資格を取る講習も受けています。毎回劣等感に苛まれ打ちのめされていますが、何とか続けています。資格が取れたら、聴覚障害者に自己表現の手段として短歌を教えて差し上げたいと思っています。教えるというと口幅ったいですが、手話が苦手で、ひきこもりがちになりやすいという中途聴覚障害者に、紙とペンさえあれば31音で思いを伝えられる短歌があることを紹介したいですね。要約筆記者の役目からは外れていますが、おかあさんはこういうやり方で寄り添いたいのです。視覚障害者の方々にも同じようなことを考えています。おかあさんも短歌を詠み続けることで生き延びてきましたので、障害者の方々にも情報を受け取るだけでなく、自らの思いを短歌で発信できる楽しさを味わって欲しいと願っています。発信する相手は自分自身でも良いのです。自分に発信するということは、自分を客観的に知ることだと思いますので、自死遺族の方々とも共に勉強できると良いのですが……。実現させるのは大変でしょうが、これらがおかあさんの今の目標になっています。
日出美ちゃんは人さまの命を救おうとして、自分の命と引き替えてしまいました。悲しいことですが、悪性高熱症の患者さんを救いたいと願って行動したのは立派でした。だからおかあさんも日出美ちゃんの生き方に近づくために、自死遺族の方々や障害者の方々に寄り添い、何か自分のできることでお役に立ちたいと思っています。先月から市の傾聴ボランティアとしても活動していますが、認知症のおばあさまの優しい笑顔に、おかあさんもにこにこ笑顔になりました。笑うことなど今後一切死ぬまでない、と思っていましたが、不思議ですね。人は変わるものですね。幸せを感じることや、目標を持つこともできるようになりましたから。
でもね、ほんとうは毎晩泣いてるの。泣きながら話しかけると写真の日出美ちゃんはにっこり笑ってくれるので、おかあさんもつられて泣き笑いになります。毎晩この繰り返しです。
おかあさんは日出美ちゃんに導かれて生きています。これから生きてゆくべき道をあなたに手を引かれて歩いています。だから独りぼっちではありません。おかあさんが一生懸命生きていれば、死ぬ時には日出美ちゃんが迎えに来てくれるでしょうか。地獄に墜ちるはずのわたしの手を取って「おかあさん、一緒に居よう」と言ってくれるでしょうか。
おかあさんは日出美ちゃんとはときどき長崎弁で話していましたね。あなたは「話せないけど分かる」と言っていました。 日出美ちゃん、愛情の足りんおかあさんで悪かったね。寂しか思いば、きつか思いばいっぱいさせてしもうたね、ごめんね。悪か親やったとに、優しゅうしてくれて、思い出もいっぱい作ってくれてありがとうね。可哀想な目にいっぱい合わせてしもうたばってん、おかあさんは日出美ちゃんばいっぱいいっぱい愛しとるよ。いっつもいっつも思うとるよ。幸せでおるごと祈っとるけんね。あと何年生きるか分からんばってん、日出美ちゃんが一緒に生きてくれとるけん、おかあさんも生きておらるるよ。ありがとうね。
日出美ちやんごめんねありがたうね
仰木奈那子(針馬ナナ子)さん
仰木奈那子歌集『日出美ちやんごめんねありがたうね』は、その題名通り、32歳で自死した娘への詫びと感謝の歌を収めています。
2014年4月、娘は慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程に入学しました。世界初の、iPS細胞を用いた悪性高熱症の研究に取り組むためです。悪性高熱症は麻酔を契機として発症し、死に至ることもある難病ですが、その原因等は未だ解明されていません。麻酔科医の娘は悪性高熱症の 患者さんと出会ったことがあり、何としてもこの病気を解明したいという思いを強くしたのでしょう。
しかし、麻酔学教室に所属し、(麻酔学教室ではiPS細胞を用いた実験は行いません)生理学教室との共同研究という特殊な立場上、実質的指導者も無く、仲間もいない独りきりの研究開始でした。しかも、麻酔科医として、週1度の静岡の病院勤務、月2度の大学病院のICU当直、他病院の当直、オンコールなどもこなし、いずれもその仕事を終えると研究室に直行して実験を続けていました。患者さんへの研究協力依頼、大学における倫理承認手続きなども一人で進めました。
2015年6月、研究開始後1年で得られた結果を記した発表要旨がアメリカ麻酔科学会に優秀演題として採択され、10月にサンディエゴの学会で口頭発表することが決まると、娘は実験量を2倍にすると言い、朝から夜中まで実験を続けるようになりました。勿論、麻酔科医としての仕事もこなしながらです。こういう状態で、さらに実験量を2倍にするという決断は、娘がどんなに追い詰められていたかを物語っています。実験で思うような結果は出でず、(自分が思うのと反対の結果が出ると言っていました)疑問、質問に答えてくれる人も無く、ただ独りで苦しんでいたのです。今の私にはそれが分かりますが、当時の私は、娘が世界的研究者になることを夢見て過剰な期待をかけ続けていました。実験量を2倍にすると聞いた時は、娘の体を心配するより、その根性を頼もしく思いました。
2015年8月16日、「おかあさん、話がある」と帰って来た娘は、自殺未遂したことやその他の辛く苦しいことを打ち明けました。それまでにも、指導者不在や孤独の苦しみは聞いていましたが、「研究は楽しい」と言っていましたし、いつも笑顔でいましたので、自殺未遂するほどの苦しみに耐えていたとは全く気づきませんでした。
娘の表情はこの日を境に一変しました。笑顔が消え、会うたびに瞼を泣き腫らしていました。私に本当の表情を見せるようになったのです。
しかし、私は娘の気持ちを理解しようとせず、いつも通りに励まし、時には責めて、娘がサンディエゴに行くことを望みました。
9月24日夜、電話すると、娘は「独りぼっち、逃げ出したい、もう嫌だ」と泣き叫びました。逆上した私は「そんな責任おかあさん負えないからあんた一人で負いなさい」と怒鳴りつけました。娘は黙って洟をすすっていました。
25日夜10時頃、娘に電話しましたが出ません。ピッチにも出ません。「ああ、日出美ちゃんが死んだ」と思いました。「責任感の強い子だから、最後の仕事をやり遂げて死んだのだ」と思いました。最終の1つ前の電車で娘のマンションに向かいましたが、体の震えが止まりませんでした。恵比寿や 渋谷から乗り込んで来る若者たちの中に娘の姿を探しましたが、居ません。
娘は亡くなっていました。私に、1年半耐えに耐えた苦悩を打ち明けた日から、40日後のことでした。娘は死の覚悟をしてそれまでの苦悩を打ち明け、私のために40日を生きてくれたのだと思います。そして、最後の電話で「おかあさんは私を分かってくれない」と絶望したのでしょう。私が娘を殺しました。
苦しみの日々が始まりました。どんなに自分を責めても責め足りませんでしたが、今死んでも娘の所には行けない、会うこともできない、それならばどんなに苦しくても生きて、娘の写真と話そう、遺骨を抱こう、生きていれば夢で会えると思って、1日1日を堪え忍びました。
詫び続けているうちに、娘の愛の深さに気づき、私もまた娘への愛を深めてゆきました。生きていた時に今のように愛してやることができていれば、娘を死なせる事はなかったのではないかと悔やまれてなりません。
今年の7月末、娘の書き残した文を見つけました。12歳、小学6年の終わり頃に書かれたものです。
「物質が生命と関わることで物質としての真の役割を見出すのなら、人間は人を愛することで人間としてどう生きるべきなのかということを見出すのではないでしょうか」
娘は愛の人でした。だからこそこんな愚かな親を許し、愛してくれたのです。長じては、人の命を救うための研究に取り組み、結果的には自分の命を自ら断ってしまうことになりましたが、娘は人間として生きるべき道を、医師・研究者という職業の中に見出し、愛に満ちた32年の生涯を生ききったのではないでしょうか。あらためて自分の罪深さを思いますが、私も娘を愛することによって、自分の生きてゆく道を見出そうと模索しています。
日出美ちゃん、こんなひどいおかあさんを愛してくれてありがとう。おかあさんは今もこの世で一番幸せな母親です。32年間、苦労かけてごめんね。良くしてくれてありがとうね。おかあさんも日出美ちゃんをいっぱいいっぱい愛していますよ。
子のまことの心の叫び受け止めてやらざりし悔い身を食ひ散らす
恋ひ慕ふらしき人とのツーショット子は甘やかにほほゑみてをり
あたたかく優しき娘にありしこと知らするやうに咲けるなでしこ
子を亡くしし親の後悔突然に津波となりて立ち上がり来る
一人子を自死させし罪は深かりき蜘蛛の巣に雨粒とどまりてをり
無能なる親ゆゑ娘を死なしめて後悔ぢりぢり身を焼きてをり
背に日差し浴びながら詠む子への歌あたたかくあれほのぼのとあれ
一人子を亡くして何もかも無くし記憶のひだは閉ぢられてゆく
一人娘は親孝行にありけりとしみじみ思ふ雨の降る昼
冬の夜は厚手のピンクのバスタオル掛けて眠らする娘のお骨
窓を打ち涙のごとく落ちてゆく雨粒見つつ我も泣きをり
雪降れば亡き子を思ふ降る雪は亡き子の涙天よりの涙
ああ娘よ今年は春が見ゆるなり桜に心が動きゆくなり
娘と共に生きし三十二年の歳月を目を閉ぢて思ふ心に思ふ
愛しても泣きても詫びても娘には届かざる両手空に差し伸ぶ
『日出美ちやんごめんねありがたうね』(短歌研究社)より抜粋
困難を表現すること――個にとっての重みに辿り着くために
水谷みつるさん
◇半分、正しくて、半分、間違っていた
1991年4月27日土曜日、私は2歳年下の弟を自殺で喪った。「軽い精神分裂病(現在の統合失調症)の初期」と診断されて3週間経つか経たないかの出来事だった。
精神科病院に入院中だった彼は、週末の一時帰宅のため、前夜から実家にいた。私は当時、新米の美術館学芸員として土日もなく深夜まで働く日々を過ごしていたが、その日は夜には出勤する約束でオフをもらい、弟に会いに行くことになっていた。だが、午前中から昼にかけて別の用事を二つほど済ませ、午後半ばに実家に辿り着いた時にはもう遅かった。弟は私を待っていてはくれなかった。前夜に母に「死にたい」と打ち明けた彼と、久しぶりの空き時間にほっと一息ついていた私の時間の流れは、違っていたのだ。
弟は、夜遅くに両親に伴われ、警察から白木の棺に入れられて戻ってきた。「損傷が激しい」という理由で、私は遺体に会うことも許されなかった。その夜、両親の部屋で(両親は別室で棺に付き添って寝た)一睡もできずに考え続けるなかで、私は3つのことを決意した。
「自殺や精神疾患をstigmatizeもromanticizeもしない。差別も聖別もしない。だから、精神分裂病と診断されていたことも含め、決して隠さない」
「(弟の死にまつわるすべてのことを)決して後悔しない」
「90歳で老衰で死ぬのも、24歳で自殺で死ぬのも、死という意味では等価であると思う」
人は必ず死ぬ。生きていれば、人の死に遭遇するのも避けられないこと、当たり前のこと、ありふれたこと。特別なことじゃない。自殺だからと言って、苦悩の末のヒロイックな悲劇のように語りたくも、語られたくもない。精神疾患もまた、生きていればかかり得る、ありふれたもの。特別なことじゃない。「狂気」などというものものしい言葉を使って、あたかも繊細で鋭敏な感受性の帰結のように語る言辞は、拒否したい。
つまり私は、日々、起こる諸々のことと同じように、それらと同等のものとして、弟の死を淡々と受け止めようとした。いま思えば、その後、起こり得ることを直感的に察知して、そう決心することで、自分の感情にロックをかけようとしたのだろう。
この私の決意は、半分、まったく正しくて、半分、徹底的に間違っていた。でも、その半分の間違いに気づくのに20年以上の歳月と自分自身の精神疾患への罹患が必要だった。
10年近く頑なに決意を守り続けたあと、2000年に精神科に通わなければならなくなって、初めて弟の死をめぐる自分の感情に向き合い始め、それからまた10年近くかかってようやく治療のなかで本当の意味で語れるようになり、そしてさらに年単位の時間をかけて、やっと自分は実にたくさんのことを深く、深く後悔していたのだと認められるようになった。
弟の自殺は、確かにこの世の中で数限りなく起こっている出来事の一つ、ありふれたことだった。また、スティグマ化されるべきものでも、ロマンティックに語られるべきものでもなかった。
でも、私にとってはとてつもなく大きなことで、一生かけて向き合い、考え、抱えていくような性質のものだった。そして弟にとってもまた、ありふれた、よくある、しかし、命を絶つほどに苦しい状況だった。だから死んだ。
◇困難を外に出して初めてわかること
「支援とアート」というテーマで依頼されたこのテキストを、遠い過去の思い出から始めたことをどうか許していただければと思う。
精神障害や疾患、トラウマ、あるいは何と名指されなくてもさまざまな困難を抱えて生きる人(むろん私もこれを読んでいるあなたも含めて)の表現(注1)について考える時、あの夜、眠れぬ頭で必死に考えていた私が心から望んだことと、それゆえに誤ったことをどうしても思い出してしまうのである。
望んだのは、偏見やその裏返しとしての過度の空想化、ロマン化に陥らずに、目の前の出来事をとらえること。しかし、特別視を避けようとするあまり、そのことの個にとっての意味や重みを取り逃してしまった。振り返ればそれは、受けとめきれないほどの大きな衝撃のなかで、衝撃自体を否認するためでもあった。
あることの個にとっての意味や重みを測ることは、とても難しい。とくに、わけもわからないまま困難なことに巻き込まれ、すっぽり呑み込まれて、自らの内も外も区別できずに溶け込んでしまっている状態(注2)だと、それが大変なことだとまず本人がわからない。ただしんどい、苦しい、うまくいかないと感じるだけで、何がしんどいのか、何に困っているのか、その輪郭も中味もわからなければ、大変なことだと認識さえできないのだ。そして、大したことない、なんとかできない自分が悪い、等々と思ってしまう。
大変だとわかるには、困難に呑み込まれ溶け込んで内も外もわからない状態から、自分と困難を分け、困難を外に出して、眺め、それが何だかを知ることが肝要である。「外に出す」とは「表現する」ことであり、表現して初めて、眺めることが可能になる。このそれ自体、難しいことを一人でやり遂げるのは不可能ではないが、表現の受け取り手として、表現すること自体を触発し、可能にする他者の存在があれば、大きな助けになる。
私は、上に書いた通り弟の自殺を決して隠さないと決め、近しくない相手に時候の挨拶とほとんど変わらない調子で「ごきょうだいは?」と聞かれた場合でも、「弟がいたけど、自殺で死にました」とぶっきらぼうなまでに直截に答えていた。しかし、そこには一切の感情が伴っていなかったし、ほとんどの相手は絶句するので、話がそれ以上、進むこともなかった。
反対に感情があふれ出てきた時は、まったく言葉にならず、ただ号泣するしかできなかった。自身が治療を始めてからは、治療者たちや稀にそれ以外の人にそれなりに長く話すようになったが、やはりあまり感情が出てこなかったし、取り乱すこともなかった。
だが、5年前にグループセラピーで初めて、同じくセラピーを受けている数名の当事者を前に「弟は自殺した」と切り出そうとした時、それまでとはまったく違うことが起こった。言葉を絞り出そうとしても出てこず、治療者の助けを借りてなんとか話し始めると、自分でも驚くほどにどんどんと感情が湧いてきた。
そして、一通り語り終えた時には、身体が自分では支えられないほどぐったりと重くなっていて、椅子に座ったまま腰から二つ折りになり、前のめりにぐにゃりとくずおれてしまった。
弟の死をめぐる感情と言葉が、死後20年経って、初めて絡まり合った瞬間だった。そうして初めて、感情と言葉がつながることが、どれほど――身体が支えを失い、地の底に引きずられるように重くなるほど――大変なことだったのかを理解した。だから、感情と言葉を切り離さなければならなかったのだ。
これは、切り離して、なかったことにしていた感情を言葉とともに「外に出す」すなわち「表現」して初めてわかったことであり、その「表現」は受け取り手がいて初めて可能になった。それ以前に治療者たちを前に話をしていた時は、もしかしたら感情を置き去りにしたままでも了解してもらえると、言葉をただ投げ出して平気だったのかもしれない。
しかし、自分と同じような、それぞれに傷つきと痛みを抱えた当事者、すなわち仲間の存在を受け取り手として感じた時、ぺらぺらの言葉でも、感情の大爆発でもない、二つがつながった、不完全でも全体性を備えたものを差し出す、何か責任のようなものを私は感じたのではないだろうか。それで、それまであいだを塞いでいた見えない隔壁になんとか通路を開けて、感情と言葉をつなごうともがいたのだ。
この時、私は、自分の語りが十全に受けとめられたと感じたわけではなかった。20年間、ばらばらだった感情と言葉を途切れ途切れにつないで吐き出したのだから、受け取る方も受け取り切れなくて当然だっただろう。私にはすべてのエネルギーを使い果たしたような疲れと、何か違うという漠然とした苛立ちが残った。
しかし重要なのは、「表現したもの」がその場で丸ごと理解され、受けとめられることではなく、そのようにつないで「表現」として出す場がたとえ一度でもあったこと、そして、他者のいるその場の光景が自身の身体の感覚とともに記憶に残ることである。その記憶は、その後の「表現する」ことを支える拠り所となるだろう。実際、私はこの時をきっかけにして、弟の死をめぐるグリーフと本気で向き合えるようになった。
もちろん、苦しいことを外に出したからと言って、すぐに何かが変わるわけではない。でも、何度も言葉で、あるいは別のかたちで、表現しているうちに、抱えていたものをさまざまな角度から眺めることが可能になり、その輪郭や中味がおぼろげながらでも見えてくることがある。
そのなかに溶け込んでいる時は、その存在すら認識できなかった困難の大きさも、相変わらず圧倒されるほど巨大かもしれないが、つかめてくるだろう。苦しいこと、つらいこと、困りごとのサイズや輪郭や中味――個にとっての意味や重み――が見えてくれば、問題は解決しなくても息がつけるようになるし、対処の方法を探すことも可能になるかもしれない(注3)。
先にも言ったように、この作業を一人で行なうことは不可能ではない。ノートやPCに思いや考えを書き、読み直し、また書くというサイクルを繰り返して、目の前の問題や状況を整理している人は多いだろう。しかし、呑み込まれるほどの困難に直面している時は、やはり表現を可能にし、受け取り、ともに眺めてくれる他者の存在が重要である。自分を苦しめているものを表現することは、時に逃げ出したくなるほどの痛みを伴い、持てるエネルギーのすべてを奪っていくことだから、一人で続けるのはとてもしんどい。でも、伴走してくれる人がいれば踏みとどまりやすくなるし、それが仲間であれば、互いに支え合うことも可能になる。また、他者とともに眺めることで、一人では気づけなかったことに気づき、その発見がさらなる表現の動機になることもある(注4)。そして何より、人とのつながりの回復になる。
◇「アート」のジレンマと醍醐味
そのような表現の場や機会として機能し得るものは、制度的なものからそうでないものまで多様にあるだろう。精神保健の分野では、各種の治療セッション、自身の抱える苦労のパターンを仲間とともに研究し、解明していく「当事者研究」(注5)、自助グループのミーティングやわかちあいの会(注6)、治療枠組みでなく行なわれるさまざまな創作活動(注7)、アーティストとのコラボレーション(注8)などが考えられる。
私は偶然を含むいろいろな出逢いによって、主に治療セッション(サイコドラマ、アートセラピーを含む)と当事者研究、そして少しだけ自助グループに助けられてきた。でも、治療枠組みの外で行なわれる創作活動やアーティストとのコラボレーションの機会に出逢っていたら、そちらを表現の場や機会としていたかもしれない。しかし、そうした場や機会自体が多くは存在しないこともあり、残念ながら巡り逢えずにここまで来ている。
大切なのは表現し、それが受けとめられる場や機会があることである。今回のメルマガのテーマが「支援とアート」であることや、私自身が病気で離職する前は現代美術を専門とする学芸員であったことを考えると、他と比べた場合のアートの特殊性や優位性を強調すべきかと思うが、正直、ほどほどに機能している場や機会で、その時のその人に合ったものであれば何でもいいと考えている。一つひとつが違うし、一人ひとりも違うし、一人もつねに同じではないから、何が「よい」といった一律の解はない(注9)。
もちろん、アート(造形だけでなく文芸やパフォーマンスなども含めて)にはアートならではの特徴と強みがある。そのなかから本稿では、アートが他と大きく異なる点について二つだけ触れたい。
一つは、虚構、嘘が許されること。これは、「本当」のことを表現しなければならないというプレッシャーから当事者を解放し、遊びや工夫や一休みを可能にする。
もう一つは、展示や出版、公演などを通して、不特定多数に向けて表現を公開、発信できること。人や社会との接点を失いがちで、孤独感や疎外感に苛まれがちな当事者にとって、ふだん活動をともにしているコミュニティを超えた、より大きなコミュニティとの連絡の回路が開かれることには、さまざまなプラスの意味がある。
だが一方で、表現の受け取り手の幅が広がることによって、受け取り手とのあいだに距離の問題が生じることには留意しておく必要があるだろう。日頃、活動をともにしていればよく起こること、たとえば、誰かの一見とても些細な表現(ちょっとした仕草や表情の場合だってある)に、あれっ?と引っかかったり、おおっ!と感嘆したり、ワクワクドキドキしたり、じーんと胸を打たれたり、それによって自分の表現が変わったりといったことは、遠い受け取り手とのあいだでは起こりにくい(そうした瞬間こそ貴重でおもしろいのに!)(注10)。
むろん時間と空間を長く共有したからといって、一つひとつの表現の個にとっての意味や重みを感じ取れるようになるとは限らない。しかし、そこに至るプロセスやコンテクストを知らなければ、感じ取ることはいっそう難しくなるだろう。
ここに当事者の表現を「アート」として(注11)一般に公開する際のジレンマと、そしておそらく醍醐味がある。表現のプロセスやコンテクストに障害や疾患が深くかかわっている場合、一般の受け取り手はそれを知り、理解する必要があるだろうか? 障害や疾患に対する偏見やスティグマ、あるいは逆にロマン化された思い込みが、受け取り方を左右する可能性はないだろうか? 反対に、表現が偏見や思い込みを変えることもあるのではないだろうか? いやいや、そんなことは置いておいて、ただそれぞれの表現の個にとっての意味や重みを、同じく個として受け取りたいと願う人もいるのではないか? そうやって、弟が自殺したその夜に私が望んだこと、犯した間違い、両方が表現の送り手と受け取り手のあいだで、さまざまに変奏され、こだまするだろう。さらに、アートには「価値」や「評価」といった問題がつきまとう。優れている、優れていない? おもしろい、おもしろくない? アートの価値って? そもそも、アートとは、表現とは何? 送り手も受け取り手も自問することになり、議論が生まれるだろう。
◇「『何者』にもならなくていい」
最後に、ここまで書いてきたことすべてにかかわることとして、宮地尚子の『トラウマ』から、私自身がずっと支えとしてきた言葉を紹介して終わりたい。宮地は、トラウマを原動力としたアートの例を紹介したあとで、大事なのはトラウマから素晴らしい作品が出来上がることではなくプロセスだと述べ、同書をこう締めくくる。
「何者」にもならなくていいということ。それがトラウマからもたらされる想像力や創造性の帰着点です。そして、それがまた新たな想像力や創造性の原点となるのです。(注12)
私はこの言葉を、苦しんだ経験を「生かし」て、アーティスト、表現者という意味だけでなく、どんな意味でも「何者」かになろうとしなくていい、という呼びかけとして受け取りたい。
トラウマの文脈だとPTG(Post-traumatic Growth 心的外傷後成長)と言われるようなものを期待されるのは息苦しい。障害や疾患や困難を得て苦労したからといって、別に成長しなくてもいい。「よく」ならなくてもいい。嫌な部分、困った部分が残ったままでいい。ただ、抱えているわけのわからないものを何らか表現して、一息ついて、人や世界とどこかでつながって、生きていければいい。
そうすれば、もうちょっと表現を続けようかと――つまりは、自分とかかわり、世界とかかわることを諦めずに続けようかと――たとえ消極的にでも思えるようになる、かもしれない。それが表現することの帰着点であり、原点になると思う。
注
(注1)「支援とアート」というテーマは非常に大きく、かかわり得る領域も幅広いが、本稿では、私自身が当事者である精神保健関連領域の支援および自助活動に焦点を絞って書く。
(注2)これは、必ずしも障害や疾患や困難が他者から見て重度だったり、認知されやすいものだったりすることを意味しない。外から見て軽度だったり、名前のつかないことだったりしても、本人にとって非常に大きな困難になっていることはよくあるし、軽度だったり名前がなかったりすればこそ、あまりに当たり前の日常になってしまい、何だかわからないままに呑み込まれてしまうこともある。
(注3)北海道浦河町の主として精神障害をもった人たちのコミュニティ「べてるの家」では、よく問題は「解決」しなくても「解消」されると言う。べてるの家は、あとで述べる「当事者研究」の発祥の地であるが、当事者研究では、さまざまな困難を抱えた当事者が、仲間と対話しながら自らの苦労のメカニズムを解明していく。そして、研究を通して見出した苦労への対処法を「自分の助け方」と呼び、仲間たちの共有財産としていく。
(注4)私は「ともに眺める」ことの重要性を、数限りなく受けてきた治療セッションと当事者研究から学んだ。当事者研究における、ともに眺め、探究することの意義について、綾屋紗月と熊谷晋一郎は、「体験の一次データについては本人がいちばんよく知っていても、その解釈については本人がいちばんよく知っているとは限らない(中略)。そこで共に解釈作業に取り組んでくれる仲間の存在が必要になる」と表現している(綾屋紗月・熊谷晋一郎『つながりの作法――同じでもなく違うでもなく』NHK出版生活人新書、2010年、128-129頁)。
(注5)当事者研究については、注3および注4も参照のこと。
(注6)依存症のグループ・ミーティングや死別体験者のわかちあいの会など、さまざまなものがある。
(注7)精神科病院で行なわれている創作活動としては、たとえば、安彦講平が東京足立病院(東京都足立区)、平川病院(東京都八王子市)、袋田病院(茨城県久慈郡)で開催している「造形教室」などがある。
(注8)日本では近年、広く「コミュニティ・アート」あるいは「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」などと総称されるようなアートの潮流がますます大きなうねりになっており、アーティストと多種多様なコミュニティとのコラボレーションの事例が増えている。とくに、東京オリンピック・パラリンピックを見据えて昨年、発表された「東京文化ビジョン」で、「障害者アートへの支援や障害者の鑑賞・参加を促す活動の推進等、文化の面でバリアフリーな都市として認知される取組の展開」が主要プロジェクトの一つに規定されたなどのこともあり、障害のある人とアートをつなぐ取り組みが盛んになっている。精神障害や疾患の当事者とアーティストのコラボレーションも行なわれている。
(注9)ただ、日本の精神科医療を取り巻く現状において、ほどほどに機能している場や機会で、その時のその人に合ったものに辿り着くのは易しいことではなく、私自身もかなり彷徨ったことを付記しておく。
(注10)日々の活動のなかで生まれる、そのままでは消えてしまいがちな味わい深い表現を、見て触れるかたちにして幅広い受け取り手に届けることに成功した興味深い事例として、東京都世田谷区の就労継続支援B型事業所「ハーモニー」の「幻聴妄想かるた」がある。医学書院から『幻聴妄想かるた』(2011年)、ハーモニーから『新・幻聴妄想かるた』(2014年)が出版されている。http://www.geocities.jp/harmony_setagaya/index4.html
(注11)美術の領域では、プロセス自体を「アート」として提示することは1960年代から始まっている。日常の些細な表現や協働のプロセス、人と人との関係性など、通常はコミュニティの内部に留まっているようなことも、「アート」ととらえ直すことで広く社会に向けて提示することが可能になる。
(注12)宮地尚子『トラウマ』岩波新書、2013年、251頁。
*『α-Synodos』vol.193(特集:支援とアート)、2016年4月1日より転載
母が遺してくれたもの
岩倉瞳さん
高校3年、受験を控えた冬。進路への不安をこぼすと、母は「あんたなら出来るよ。やれるだけやってみな」と返してくれた。そして、「お金ばかりかかってごめんね」と謝る私に、母は小さなため息をつき、穏やかな笑顔で言った。「あんたも親になれば分かるよ」と。そんな日が来るのだろうか。遠い未来に想いを馳せつつ、母と、私と、まだ影も形もない子どもと,3世代が並ぶ光景をぼんやり想像して、少し照れ臭いような、温かな気持ちになった。
あれから干支が一回り以上、相当の年月が流れ、私は3児の母親になった。
しかし、私の母が孫を抱くことはなかった。
大学4年、就職活動盛りの春。母は自らいのちを絶った。遺書はなかった。
唐突に突きつけられた現実に、葬儀前後のことはよく覚えていない。唯一、脳裏から離れないのは、涙声で私の身体を気遣う、電話越しの母の声だ。母が息絶える直前に会話をしたのは、私なのだ。
母とはよく話をした。地元を離れてからも毎週欠かさず電話をし、ありふれた会話をたくさん交わした。お日様のように明るかった母の声色が変わったのは、最期の一年だ。
職場の配置転換をきっかけに、母は電話口で泣くことが増えた。それだけでなく、親族との死別、子どもの巣立ち、自身の更年期。振り返れば、あの年は色々なことが一気に母に降りかかったのだと思う。恐らく母はうつだった。しかし、当時の私はそれに気がつくことができなかった。遠方で学生生活を送っていた私にできることは少なく、ただ母の話を聞き、母の気持ちが落ち着き次第、受話器を置くようなことが幾度とあった。
あの日は、土曜日だった。
いつものように母からの電話を取ったものの、泣きじゃくる母の言葉が聞き取れず、全く会話にならない。少し時間を置けば母の気持ちが落ち着くと思い、私は一旦会話を終了させる提案をした。この判断が今でも悔やまれる。
「身体に気をつけて・・・」やっと聞き取れた、振り絞るような母の声。それが、母の最期になった。数時間後、仕事から自宅に戻った父が、変わり果てた母の姿を見つけることになる。
母が最期に助けを求めたのは、私だった。
すがるような思いで、私に電話をかけたのだろう。
けれども、私はその思いに応えることができなかった。助けることができなかった。
果てしない後悔が私を蝕み、絶望感を抱えながら、社会人になった。
私の大きな転機となったのは、結婚をし、子どもが生まれたことだ。人は1人では生きられない。ふやふやの赤ん坊の世話をしながら、自分がいかに周囲に守られ、大きな愛で育ててもらったのかを知った。そして、亡くなった母が望むのは、懺悔ではなく、私自身の幸せなのではないかと思うようになった。言葉にすれば当たり前かもしれないが、自分自身が母親としての視点を得たことで、リアリティを持って母の思いを想像するようになった。
その後、私は自殺対策に取り組む民間団体に所属し、様々な自死遺族の方と出会った。「自殺で家族を亡くす」点は共通していても、人の人生は一人ひとり違う。いのちとは、どれもが尊く、唯一無二のかけがえのないものだと、まじまじと思い知った。
時間の流れは残酷で、大好きだった向日葵のような母の笑顔も、だいぶと遠くなった。日常生活は絶えず動き、様々な波がやってくる。けれども、今でも変わらず私を突き動かしているのは、「あんたなら出来るよ」という、耳の奥に残る母の口癖なのだ。母は私の中に、勇気づけの芽を遺してくれた。
願わくば、私も母を勇気づけたい。その存在を全力で肯定したい。母の代わりは、この世界中のどこを探してもいないからだ。人は生きているだけで、誰かを幸せにしている。私は、母にただ生きていて欲しかった。けれども、その母はもういない。それならば、今の私にとって大切な人達や、これから出会う人に寄り添い、まるっと受容した生き方をしたい。傷は癒えても、決して消えることはない。それでもいいのだと、16年の歳月を経て、ようやく思えるようになった。自分の足で、一歩ずつ。これからも生きて行こうと思う。
娘から突き付けられた、家族の自死による影響…そして分かち合う
-命の大切さを自覚していたのに-
吉永洋子さん
2009年のゴールデンウィーク明け、他県に進学して、一人暮らしをしていた、大学2年の娘が意識不明という連絡が、在籍中の大学から入りました。嫌な予感をしながらも、運ばれた病院からの「治療中」「一刻も早く」という言葉にすがり、家族と相談をして、一人で車にて県境を越えて、病院に駆けつけました。
病院に到着し、「お一人で来られたのですか」と聞かれた時に「最悪の事態だ」と実感、その後医師からの説明に「死亡ということですか」と聞き返すのがせいぜい、霊安室で対面したのは、確かに娘でした。連絡を受けた時にはすでに娘の命が終わっていたこと、しかし医師からでなければその説明ができなかったこと。なぜ、病院の勤務経験がありながら気づかなかったのか、自らを責めました。そして、「これから私はうつになる」と漠然と考えていました。
私は、元々病院の「医療ソーシャルワーカー」として精神科の病気をお持ちの方や、その他の身体的な病気により入院され、それまでできていたことが困難になった方に対して、ご本人・ご家族・地域のサービスを提供する機関と連携をして、その後の生活について考える仕事をしていました。娘の自死当時は大学にて自らの後輩となるべき「精神保健福祉士」の養成に携わっていました。
そんな私の娘が自死。職場に戻って良いのだろうかという悩みを持ちました。この悩みは、事件や事故、病気などで娘を失っていたとしたら考えられないことでした。
職業柄、当時は年間に3万人もの方が自死で命を落としていることを知識としては知っておりました。しかし、現実には目の前の仕事をこなすことがやっとで、その問題の重みまで感じることはありませんでした。
娘はもともとどこに行ってもすぐに友人を作るタイプで、充実した大学生活を送っていました。学業に励み、サークル活動を積極的に行い、友人に恵まれていました。一方で、自分に自信を持つことが難しかったようです。
自死であることを公表するかについて、「かっこ悪い、隠し通せないか」と考えましたが、私も自らが嘘をつけないタイプであり、特に娘と仲の良かった友人に「知らなかった」と言われることを避けたいと思い、冷たくなった娘の横で、自死を公表することを決めました。悩んだ時間は2,3分。このような大きなことを、家族とも相談もせず、決めてしまったこと。本当に重大なことを決めるのに、かけられる時間は少ないことを痛感しました。
家族とは直接公表をするのかという相談はしませんでしたが、暗黙のうちに認められ、おかげで、弔問・通夜・葬儀には多くの方にお越しいただきました。娘の友人、家族ぐるみの知人のほか、職場の仲間や学生・卒業生が参列してくださいました。「職場に戻って来てね。」と背中を押されたように思いました。
私たち家族が娘のアパートの片づけをしに行った時に、娘のクラスメートやサークルの先輩が集まる機会を作りました。サークルの仲間たちとは喫茶店で話をしました。その中の先輩から「俺の方が危なくて、娘さんに助けられていた」との言葉をいただきました。そうか、誰もが持っている自死行きのボタンを、娘は命の大切を知りながらも、衝動的に押し、あえて助けられないように死を選んでしまったのだと教えられました。
忌引きを経て職場復帰しましたが、娘とかつて出かけたことがある場所に行けば動悸が起こりました、職場では普通にふるまえても、一人になれば途端に涙が流れる日々でした。
娘の死から2か月半後、仕事から帰宅して自宅の車庫に車を入れようとしたところ、ふいにアクセル操作がわからなくなり、バックのまま自宅横のブロック塀に激突しました。ほかの方を巻き込む事故でなかったことはが幸いでした。この事故は、「娘が休めといっていること」と言われ、休職することを決めました。産休以来の長期休み、お墓に行きながらお寺の方と会話し、心療内科に通い、友人とのメールや会話をしながら、ぼんやりと日々を過ごしました。また、娘の友人とのメールや会話、中学時代の卒業文集などを通して、娘の自死の過程や理由を少しずつ私なりに整理することができました。そして、2か月の時を経て、職場に復帰することができました。
それでも、娘を失ったという現実に対して、受け入れられない時間がふいに訪れます。その年の大晦日、娘が生きていた2009年が終わり、娘がいない2010年が始まることを阻止しようと、意味のない力を振り絞っていました。そして命日、その時間になると必ず動悸が起きます。いわゆる「命日反応」2010年は普通に仕事を入れていたために苦しみました。そのため、命日は許される範囲で自宅にいるようにしています。
現在、自殺者は年間2万5千人を割っています。私はそのことに単純に喜びを感じます。一方で、自殺対策として「命の大切さの教育」という言葉をよく耳にします。まるで、自死者は命の大切さを知らない、粗末にしているということを前提にしているように。
自死の理由は人それぞれ、そして複雑な要素が絡み合っています。自死者も、命の大切さについては理解している、むしろ命と向き合いながら、最後に押してはいけないボタンを押してしまっただけだと考えています。
そして、自死遺族も十人十色。自死者と同じ年頃の人と会いたい人、会いたくない人。自死者の写真を見たい人、見たくない人、見たくても見られない人。お墓や仏壇にお参りをしたい人、できない人。お骨を墓に埋葬できる人、手元に置いておきたい人。公表についてもしたい人、できない人。絶対的な正解はありません。それぞれが判断していけば良いのです。
分かち合いの会のルールは「アドバイスはしない、自らの経験を自らの言葉で語るだけ。」そのため、ほかの遺族に共通点を見つけほっとすることもあれば、違う見方があることを学ぶこともあります。私にとっては必要な楽しい時間ですが、自宅に戻ると脱力状態に陥ることも多いです。この脱力状態になることまで含めて「分かち合いの会の効果」である「癒し」だと意識しながら、私は分かち合いの会に参加し続けます。娘が生きていた19年間が確かに存在し、彼女が命がけで伝えた命の大切さを実感するために。
分かち合いで、苦しみを半分に
降矢いずみ(仮名)さん
2歳年上の兄(享年31歳)を、自死で亡くして、8年が経ちました。
3月下旬の月曜、早朝の出来事でした。
オーバードーズによる自殺企図から生還し、数ヶ月間の自宅療養を経て、職場復帰、そして、妻・娘(当時・保育園児)とも、仲良く暮らしていた最中でした。
うつ病の症状はとても回復し、笑顔で活発に過ごしていたので、もう大丈夫だと安心していた段階での、青天の霹靂でもありました。
オーバードーズで自殺企図をした時は、兄は、SNSに、その苦しい胸の内を書いてくれていて、遠方に住んでいたわたしでも、その心の危うい動きを把握できていました。その時は、オーバードーズの自殺企図は防げなかったけれど、未遂の段階で、命を助けることは出来ました。
それなのに、それなのに、最期に逝ってしまった時、何故、何もサインを出してくれなかったのか。
「この大ばか者!」
亡くなった日に、冷たくなった兄の枕元に駆け付けたわたしは、悲しみよりも、その怒りで溢れていました。亡くなった人に、こんな言葉を向けるのは不謹慎だと思いましたが、それでも、怒りが悲しみに勝っていました。
あれから8年経ってみて、亡くした直後の張り裂けそうな心の痛みは、かなり小さくなりました。最初の数年は、情緒不安定になって涙が止まらなかったり、自律神経失調症や不眠に苦しみましたが・・・。
回復へのカギは、相性の良いカウンセラーに毎月1回、一年以上、根気強く付き合って頂いて気持ちを整理できたこと、そして、同じ苦しみを抱える自死遺族の方々と“苦しみを共有できたこと”だと感じています。
実は、兄を亡くして3年ほど経った時に、一度、自死遺族のための分かち合いの会に参加しました。自分なりには気持ちの整理が付いていたはずなのに、「自殺」について直視し、自分の口でその気持ちを語ったことで、その時は、涙してしまい、帰宅してからも強い抑うつ感に苛まされました。こんな辛い気持ちになるならば・・・と、その後、自然と足は遠のきました。
日常生活の中では、多くの人は、「自殺」を忌嫌います。わたしも、世間体のため、「自殺」が他人事であるように振舞っていました。ただ、やはり、わたしの家族が自死で亡くなっていることは事実であり、わたしの心は、今でも、苦しみと悲しみで傷付いていることに気づきました。
そんな頃に、ご縁があり、再び勇気を出して、分かち合いの会へと通うように。予想通り、分かち合いの会で自らの気持ちを吐露することは、苦しいものでした。初めの頃は、会の終盤に体調を崩し、嘔吐してしまったことも・・・。しかし、回を重ねるごとに、自分の気持ちを落ち着いて話せるようになり、他の自死遺族の方々の話からも、様々な自殺の側面を学び、自死遺族という、辛い苦しみを共有する仲間として、「お互いを支え合っている」という温かい絆を感じるようになりました。
傷付いた自分の心を癒すには、長い時間が必要です。ゆっくりと、じっくりと、ご自分のペースで、ご自分なりに、自分を癒していく。それも一つの方法です。
ただ、視野を広げてみると、自殺大国の日本では、36.9 - 43.7人に1人が自死遺族に該当します(森ら,2008)。世間には、似たような苦しみを抱える仲間がたくさんいるのです。そして、有難いことに、公的に、自死遺族を支えようと活動して下さっている方々も。 そういった仲間と手をつなぎ合い、その優しさに身をゆだねれば、わたし達の心の苦しみは、ずっと早くに半減するように、わたしは実感しています。
兄の命を助けられなかったことは、今でも、とても心残りです。
そして、兄の自死は、家族、友人や職場の方々に、深い悲しみだけでなく、強い苦しみも与えました。
自殺は防ぐことが出来る死。
1つの自殺を防げれば、悲しみと苦しみの連鎖も防ぐことになります。
残された家族は、精神的にも、経済的にも大変な苦しみや困難を抱えていますが、残されたわたしたちが自分達の人生を無事に全うすること、出来れば、充実した幸多き人生を送ることが、亡き人への供養にもなると思います。
今もまだ、絶望の淵で、孤独に苦しみと闘っている自死遺族の方がいたら、わたしが辿った回復へのプロセスが参考になれば大変幸いです。
さあ、勇気を出して、一歩前へ。
わたし達は、これからも、生きて行くのですから。
2015年12月末日
(引用文献) 森浩太・陳國梁・崔允禎・澤田康幸・菅野早紀(2008)日本における自死遺族数の推計.日本経済国際共同センター.ディスカッションペーパー. 1-13.
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_depressive.html
夫と伴に
戸倉由紀枝さん
うつ病への認識の甘さ
私の夫は約二年間うつ病を煩い、回復期に二人が暮らしていた部屋で大量の安定剤とお酒を一度に摂取し、この世を去りました。夫はうつ病になってからはお酒を一切飲んでいませんでした。安定剤とお酒の大量摂取は、うつ病による発作的な行為だと私は思っています。
夫の調子が悪くなり、亡くなる前日に私は夫を病院に連れて行きました。私は医師に、入院を夫に勧めてほしいとお願いしました。しかし、本人が嫌がり医師が大丈夫だろうと判断したので、入院せず帰宅しました。私は、夫を入院させなかったことを今も後悔しています。
うつ病は、まだ解明されていないことが多いですが、脳の神経伝達物質の働きが悪くなることで起きると言われています。またストレスなどが引き金になる場合もありますが、何も原因がないまま起こる場合もあるそうです。注1
うつ病による希死念虜は、本人の気持ちの持ち方や家族の愛情でも止めることはできません。主治医も私も夫も、うつ病による希死念虜について認識が甘かったのだと思います。
私は生きる、そして誰も責めない
夫はやさしくて頼りになり、私にとって一番大切な人でした。夫の死により私が信じていた全てが崩壊し、私の生きる価値はなくなったも同然でした。しかし、私が死んだら家族はもっと悲しむ。夫の死を巡り家族が責め合えば、家族はもっと不幸になる。だから私は死んではいけない。私の心に誰かを責める気持ちが生まれても、それを本人に言ってはいけない、ととっさに思いました。
「一心不乱に泣き、できるだけ自分が安心できる人としか会わないこと」
若くして配偶者を亡くした友人の言葉に、私は従いました。また、夫の死のショックから、私自身がうつ病になる可能性もあるので、不眠と体重減少が続く場合は、躊躇せずに病院に行こうと決めました。
号泣する日々
絶望、悲しみ、後悔、自責の念、怒り、戸惑い、無力感、喪失感に襲われ、夫の死後約3ヶ月間、私は毎日号泣していました。うつ病を理解しない社会、医師、病院関係者、家族、友人、私を遺して逝った夫、神、私自身、全てに怒りを向けました。
「…すれば良かったのに」「がんばって」「早く忘れて」「立ち直って」「運命だから仕方がない」「ペットや友人を亡くして悲しかったから気持ちがわかる」「あなたは恵まれている」こうした周囲の人たちの言葉に、私は傷つき、怒り、時には発作的に死にたくなりました。言った人たちは、悪気はなく私を元気付けたかったのでしょう。しかし、私に心の余裕はありません。このままでは私と周囲の人たちは傷つけ合うことになると感じ、心療内科のクリニックに通うことにしました。私の希望で薬は処方してもらわず、カウンセラーに自分の感情をただ語るだけです。
励ましも慰めの言葉もいらない
周囲の人から言われて傷ついた言葉を、夫の生前私も多くの人に言っていたことに気付きました。
励ましの言葉は私の感情を否定し、慰めの言葉はその人の想いの押し付けにしか感じられませんでした。慰めになったのは、私の感情や想いを否定せず、意見せず、判断せず、評価せず、解釈せず、何かと比較せず、ただ聞いてもらうだけです。
家族、友人、自死遺族会、カウンセラー、教会の牧師夫妻、電話相談に、私は夫への想いと様々な感情を言葉にし、話し続けました。すると、号泣ではなく静かに涙を流す日が多くなり、泣かない日も増えました。同時に私の生きる価値が再構築され、周囲の人たちへ改めて感謝の気持ちを持てるようになりました。また、自分自身と他者への怒りを許しに換えるための努力をしています。しかし、今もふとしたことで、悲しみ、後悔、怒りなどの感情が一気に溢れ出ます。決して消えることのないこの悲しみを、大切に抱えて生きていくつもりです。
夫と伴に
私は、今も夫と繋がっていると感じます。「私も死にたい」と私が夢の中で泣いていると、「死んで僕が喜ぶと思う?」と夫は言い、「誰のせいでもなく、うつ病だったから仕方がなかったんだよ」と、夫は何度も夢で私に伝えてくれました。
命には必ず終わりがきます。私は自分の命を終える日を楽しみにしています。それは、死後、夫と再び会えると信じているからです。私は生かされている限り、その日を大切に生き、うつ病や自死を少しでも多くの人々に正しく理解してもらうこと、遺族支援など、夫の想いと伴にできることをしていきたいと思います。
約束の向こうに
佃祐世さん
私は、夫との約束「司法試験を受験すること」を心の拠り所にして、夫が自死した後も、司法試験の勉強をすることで何とか生きてきました。
今私は、弁護士として、日々仕事に励んでいますが、夫との約束を果たしても、私の悲しみや後悔は決して消えることはありません。今なお、夫との約束の向こう側にある何かを求めて走り続けています。遺された私にできることは、弁護士として、自死の問題や自死遺族を取り巻く問題に取り組むことだと思っています。
自死する人を少しでも減らしたい。誰にも、私と同じような悲しみや苦しみを感じてほしくない。だから、自死がなぜ起こるのか、遺族がどれほど悲しみ悩み苦しんでいるのか、多くの人に知ってもらいたい。多くの人の理解と協力を得たい。そのような思いから私が書いた本「約束の向こうに」の最後に、私から皆様宛にお手紙を書きましたので、そのお手紙をここに掲載させていただきます。皆さまの心に私の願いが届きますように・・・
読者の方々へ
どうか、がんばりすぎないでください。
疲れたら、無理しないで、休んでください。
いろんなことを一人で抱え込むこともあるでしょう。
でも、一人で悩みを抱えないでください。
一人で苦しみを抱えないでください。
そして、これ以上、自分を責めないであげてください。
これ以上、自分を傷つけないであげてください。
誰かに、どこかに、助けを求めてください。
あなたの力になる人が必ずいます。
自死遺族の方々へ
もう自分を責めないであげてください。
許してあげてください。
つらくなったら、助けを求めてください。
誰かを頼っていいんです。
誰かに甘えていいんです。
笑ってもいいんです。
だから、笑うことができるようになったなら、笑ってください。
でも、心から笑えないから、笑ってもどこかむなしくなるかもしれません。
いろんなことを考えると、なかなか笑えないかもしれません。
それでも、笑ってください。
少しずつ、本当に少しずつですが、何かが変わっていきます。
あなたは、幸せになっていいんですから。
亡くなった大切な人のためにも、あなたが幸せになってください。
自死遺族の周りの方々へ
どうかそっとしておいてあげてください。
けっして、責めたりしないでください。
あなたの優しさで受け止めてあげてください。
怒ったり、泣いたり、不安がったり、いろんな感情をぶつけてくることもあるかもしれません。
受け止められれば受け止めて、もし受け止められなくなってきたら、そっと距離をとってください。
立ち直ろうと懸命にもがいているのです。
どうか温かく見守ってあげてください。
あなたの優しさをみんなへ
2014年5月
「約束の向こうに」講談社より
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062190039
自死遺族だからこそ
上田玲子さん
仲間(ピア)を求めて
2011年5月10日火曜日、東日本大震災から2ヶ月が過ぎようとするその日、当時24歳だった息子は自ら命を絶った。5月というのに不快になるほどむしむしとした日だった。
突然、思いもよらない形で息子を喪った私を様々な感情が襲った。なかでも私を驚かせたのは何かを殴りたいほどの怒りだった。経験したことのない激しい怒りに私は混乱し、このままではおかしくなってしまうのではないかと怖くなった。けれど当時ヘルパーをしていて、「うつ」と診断された利用者の方が服薬してもなかなか好転しないのを目の当たりにしていた私は、精神科の門をたたく気にはなれず、福祉の勉強をしていたときに知った同じ境遇の仲間(ピア)と気持ちを共有し、支え合うピア・サポートに救いを求めた。ネットを検索し、ライフリンクのホームページの「自死遺族のつどい」全国マップのなかでみつけたパンフレットを見て、私に起こっていることは大切な人を自死で亡くした時の自然な反応であるらしいとわかったことが、私をひとまず安心させた。すぐに最寄りの会場の日程を調べ、それからは「つどいの日まで・・・」と思いながら一日一日をやり過ごした。
偏見
10日後に息子の四十九日を控えたその日、22歳の娘に付き添われ「つどい」の会場に向かった。人目があるにもかかわらず、移動の電車のなかでも涙を止めることはできなかった。そして会場に着いた私は、そのときまでその会場の「つどい」が行政の主催であることを意識していなかったことに気づいた。そしてわかち合いの輪のなかで、「この中に自死遺族でない人は何人いるのだろう。」と思っていた。ヘルパーをしながら非営利の活動をしていた私は、利益のない活動を継続するために行政の金銭的な支援が大切であることも、当事者同士がお互いのかなしみで傷つけ合わないようにするためには時として専門職の助けが必要なこともわかってはいたが、それでもわかち合いは当事者だけでしたかった。その訳は。
私は、おそらくそのほうが楽だろうという予感から息子の自死を隠すことはしなかった。それでも幸いなことに、あからさまな偏見にさらされることはなかった。ただ息子を亡くすまで、私は「家族の愛情さえあれば人は一線を越えることはない。」そう思う母親だった。そしてその偏見に息子を喪ってから苦しめられることになった。今から思えば、私はその偏見ゆえに誰にでもは心を開けなくなっていたのだと思う。それは例えていえば、「服を着ている人の前で自分だけ裸になれない。」そんな感覚だろうか。ただわかち合いの輪の中にはいった若い行政の職員は、控えめで当事者の言葉にただ耳を傾けてくれた。そして話しながらも涙を止めることのできない私の膝の上に、誰かがティッシュの箱を載せてくれた。
「つどい」
「つどい」に参加したからといって急に何かが変わることはなかったが、お互いを傷つけ合うことが怖くて家族に胸の内を明かすことのできなかった私にとって、「つどい」は唯一自分の気持ちを語ることのできる場だった。そして、子供を亡くした遺族に鏡に映ったかのような自分をみつけたり、立場の違う遺族の言葉で自分の家族の思いに気がついたりした。
自分に向き合うのが苦しくて会場近くの公園で躊躇しているうちに遅刻してしまったり、「つどい」で発言した言葉を反芻しているうちに反対方向の電車に乗ってしまったり、そんなことを繰り返しながら2カ月に1度「つどい」に通い続けた私は、ある日、広い散らかった部屋を自分の周りだけ見ながら掃除していったらいつの間にか部屋全体がすっかり片づいるのに気づいた時のように、自分の思いが整理されているのを感じた。
かなしみを飼いならしながら
不思議な現象、深夜床に就いた時に例えは家がきしむようなほんのちょっとした物音にも目の奥でフラッシュが光る、そんな現象も息子を亡くして2年が過ぎるころから現れることはほとんどなくなった。ただ息子を喪ったかなしみは一生消えるはずもなく、油断せず、鋭く牙をむくことのないように飼いならしていくほかないだろう。だからこそ自分が幸せを感じることを許そうと思う。息子がそれを望んでいると信じて。そして、いつの日にか息子が迎えに来てくれる時がきたら、「母は、天寿を全うしたよ。」と報告したい。
2014年10月10日 記
いのちの質
佐々木浩則さん
浜松市の自死者数が最も増えた平成21年に私の妻はその対象者となった。市の第一次自殺対策推進計画の初年度でもあった。直後から、その前年に始まった浜松わかちあいの会に参加している。翌年、会の創設者から会の運営と第一次計画の専門委員を引き継いだ。
●人薬と日にち薬が“いのちの質”を高める
自死は結果。そこに至る状況や環境に想いを寄せ、寄り添う事を大切にしたい。わかちあいの会には、様々な立場や思いを持つ自死遺族が参加する。会ではよく人薬(ひとぐすり)、日にち薬(ひにちぐすり)の話が出る。支え合う人や重ねる時間が癒しになるという意味である。しかし日にち薬には賛否が分かれる。時が経っても何も変わらない、むしろ苦しみは増すばかりと言う人は多い。その違いをいつも考える。今の私の考えでは、それは人薬に左右される面があるのではないか、支え合う人や寄り添ってくれる人がそばに居て、その人たちとの交流の日々を重ねる事ができていれば、日にち薬は作用し易い。逆に人薬が不足すれば日にち薬は効き難いのではないかと思っている。そしてそれは、遺族や死にたいと思う人だけでなく多くの市民に当てはまるのではないだろうか。音楽、スポーツ、趣味、社会活動、何か興味・関心のある事を通じて人と出会い、交流する。そういう日々を重ねる事ができれば“いのちの質”が高まると思う。
●“心のがん”への理解
妻の様になるなとは誰も言わない。より良く生きる、いのちの質を高める事への理解・協力者は多い。否定や叱咤激励ではなく、認め共感し寄り添う事。妻には、励まそうとする夫、友人や医師、自分を頼りにする年老いた父や幼い息子は居たが、共感や寄り添いが不足していたと思う。私は妻の自死を否定も肯定もしない。自死を否定する事はそれまでの生き様の否定にもつながりかねない。ただその“心”に想いを寄せ、その“心”を受け継いで暮らしたい。彼女が生きた事、遺したものを大切にしたい。検視医から頂いた「自死は心のがん」と言う言葉が私の腑に落ちた。まさに心に増殖するがん細胞に蝕まれた末の死だった。がんを無くす努力はしてもがん患者を責める人はいない(以前は居たそうだ)が、自死を否定し責める人は居る。その違いは無理解だと思う。多くの自死は、個人の自由意思や選択の結果ではなく、複合的な要因により心理的に「追い込まれた末の死」であるとし、「自死に追い込まれることのない社会の実現」を目指す国の指針に賛同する。
●最終課題は死の形や数ではなく“生き方”
そのためには、自死をただ単に否定・防止しようとするのではなく“死に追い込む要因”に目を向け改善する努力が重要であると考える。浜松市はその課題への取り組みを続けている。「みんなで命の質を高めよう。自死はもちろん減っている」が望ましい。命の質が高まれば死の質も高まる。最終課題は死の形や数ではなく“生き方”であると考える。
第二次推進計画を着実に実行する中で“いのちの質”を高める活動が活発になり具体化し、次の第三次計画の目標の中心には“いのちの質の向上”が掲げられる事を願い、微力ながら参画を続けたい。
ひとりぼっちだったんですか?
南部節子さん
(略・・・)
遺書には「仕事ができない、全くできない、なんでかわかりません、ごめんなさい」と20回近く。そして「***(家族の名前)、ごめんなさい、かんにん」
なんで一生懸命働いたお父さんがごめんなさいといわなければならないのか? ごめんなさいというのなら何で私たちの元へ帰って来てくれなかったのか?
亡くなってから勉強しても何もならないのですが、それから私は自殺という文字を見れば新聞を切り抜き、テレビのビデオを撮り、本を読み、うつ病の講演を聞きに行ったり、夫の業務日誌と私の日記を照らし合わせてどのあたりから苦しんでいたのか等、調べるうちに、お父さんは悪い事してない、身勝手に死んだんじゃないと思うようになり、周りに本当のことを言えるようになりました。
最初はご近所には、心筋梗塞と伝えていました。そして葬儀も身内と会社の人だけで行いました。私の中にも自殺に対する偏見があり、夫の名誉も傷つけると考えたからです。
でも『親父は何か悪いことしたんか』と息子に言われ、娘には「お母さん、何で嘘つくの、嘘をついたらその上塗りをしないといけなくなってもっと苦しくなるよ」と言われました。
まだまだ自殺はタブー視されています、私もなんで自ら命を絶つのだろう、死ぬ気ならなんでもできるやないのと考えていましたから。
しかし確固たる信念を持って死ぬ人はいるのでしょうか? さまざまな原因で追い詰められ、もう死ぬしかない、逃げる方法が考えられず、そのときは正常な判断ができなくなり死に至るのではないかと私は思います。
病気、事故、事件で大切な人を亡くし残された者の痛みや自責の念は一緒だと思います。
ただ自殺は責める相手がありません、責めるのは自分なんです。(略・・・)
後で思い起こせば1年前ぐらいから夫は私の知り合いにもいつもは愛想よかったのに、顔をそむける事が多かったり、どこか一緒に行っても先に帰ってしまったり、魚が好きだったのに焼き魚の匂いがだめだといった事とかなんで気が付かなかったのか後悔ばかりです。(略・・・)
まだまだ自殺は個人の問題、「勝手に死にたい人を止めようがない」と言われています。 でも、人が人として、人ごととせず、悩んでいる人のサインに気づき、いろんな人が、いろんな場面で関わることができれば、生き心地のいい社会になっていくのではないかと考えています。(略・・・)
「自殺で家族を亡くして~私たち遺族の物語(三省堂)」より
「タフでなければ生きてはいけない。優しくなくては生きる資格がない」
(レイモンド・チャンドラー 正文が愛した言葉)
石倉紘子さん
(略・・・)
何のこと?
うそ!
退院したばかりじゃない!
帰ってきたら旅行に行こうって言ったじゃない!
何で私をおいていってしまったの!
死ぬまでずうっと一緒って言ったじゃない!
死ぬときは一緒っていったじゃない!
何で? なんで? なんでよ!
そんな感情が渦巻いて、長いこと蹲まっていました。
(略・・・)
京都でのお葬式後はカーテンを閉め切り、真っ暗な部屋の中でひたすら人生をのろい、逃れるようにやってきた関西で、たった二人で生きてきた人生の伴侶の心の闇を妻でありながら救うことができず、癒してあげることもできなかった自分を責め、私をおいて逝ってしまった夫を責め、ひたすらお酒におぼれ「なぜ、どうして」、と泣き喚く毎日でした。自殺未遂もしました。からだの半分をもがれてしまったような気持ちでした。
(略・・・)
1995年阪神淡路大震災では、テレビに映し出されるあまりの悲惨さを見過ごすことができず、ようやくボランティアに出ました。ボランティアの中で見たことは、自殺者、孤独死が大変多く、中には引き取り手がない遺体、葬儀も行ってもらえない遺体、数日たって発見された遺体、多くの遺体が警察署に放置されていたことなどを聞きました。
その時、私の胸に憤然と沸き起こってきた思いは、
「良い妻でなかったために夫を一度死なせてしまった。そして今度は、夫を自分が死ぬ時まで生きていた証をせずに封じ込めている。そのことは夫を2度死なせてしまうことになる。それは、今ここで起こっている事、自殺者の尊厳を踏みにじっている事と同じではないか? 生きている間にはいろいろあったとしても、それぞれは必死に生きたと思う。私の夫、伊藤正文も、一生懸命に生きていた。まじめで、誠実で、優しくて、人間が大好きだった。心から人を愛していた、誰にでも優しかった。最後には、自死という人生の閉じ方をしたけれど、決して弱いわけでも、卑怯なわけでもなかった。そんな夫を私が封じ込めていることで、生きていたことさえ否定している。
自殺ということで私自身が夫のことを恥じている、人に知られてはいけない悪いことと考えている」
私自身の中に自殺に対する大きな偏見差別があることに気が付きました。そして、正文に対して大変失礼なことをしていたことを反省致しました。
「私の夫は、平凡だけど一生懸命に生きていたよ。」と「この世に生きていた夫の生」を証ししたい、封じ込めていた夫の尊厳を取り戻し、夫の生を語ることでそのように生きた夫の死を決して無駄にしたくないと考えました。(略・・・)
「自殺で家族を亡くして~私たち遺族の物語(三省堂)」より
いのちの連鎖~つながり~
廣瀬明美さん
私の母は享年33歳でした。
本当は「誰かが助けてくれる」と思っていたように”あの時”……の背中や “生前の言葉”から感じて、第一発見者であった私は長く責任を感じていました。
長女の私を帝王切開したことで、「自力で産めなかった」という思いやその後のうつ症状などで、出産後8年近くの間、何度も何度も自殺未遂を繰り返したことが25年経った父との会話でわかりました。他にも要因はありますが、それは人を責めることになるのでここでは言いません。
自分のことを話します。
―ごめんね、おかあさん。。。。
聴いてあげられなくて、助けられなくて。あなたという人間に注意を向けられなくて。
小さい私、当時7歳(まで)の私は本当に無力でした。7歳くらいの私は母のことがわからなくて、小さい妹をみない(みられない)ことや本心では自分が甘えられないことにイライラすることもあり、我慢しながらも八つ当たりもしてしまいした。。。。これは自殺の思いに近い人への接し方ではなかったのですが、私は甘えたくて苦しくて怒りを向けてしまったのです。
母の死後、私は母の自死の発見から“フラッシュバック”や“自分の肉体と心に統 一感がない”、“自分を遠くで他人事のように見ている”症状に長らく悩まされてきま した。
成人してからは「家族から向けられた言葉」をきっかけに、自らクリニックに出向い たところ、初回に医師から「PTSD」と診断を受けました。母の自死発見後15年 ほど経過してのことです。
遺族は「子ども」もまた、もしかするとより一層、周囲にはなかなか理解されないま ま孤独に生活しているやもしれません。そして私は診断を受けて闘病しました。
私自身20代初めのうちに結婚をしていたので専業主婦であったり共働きであったり するなかで、ずっと子どもの頃から理解が困難な状況でしたが、診断によって「自分 が抱えて来たものがわかる」ことは大きな一歩でした。
そこから色んな出会いを見つけPTSDを克服することができました。
母の死は大きいけれど、それだけでなくいろんな人の死を身近にザワザワっと感じてきて、『ある人の死から、生きている私たちが、生きること(=死を迎えるまで)を学んでいる』ように思うのです。
自殺に至るまでにはサインを出している場合も多いと思います。実際に私の母も後から思えばそうでした。たくさんのサインを出していました。「明美の命の恩人って、誰かわかる?」と亡くなる数ヶ月前に話していたのを今でも覚えています。けれど、私は母を救えなかった。母の享年と同じ年齢を迎えるころ、無事に迎えられるか、死の恐怖が募り、だったら目を背けるのではなくて、自殺ととことん向き合って生きていくことを誓いました。
母のことで学び、だから「死にたい気持ち」に寄り添っていく生き方を選びました。
それとともに『自殺という死への偏見や遺族への非難、そして家族内での”語りづらさ”』など、これらを払拭するために啓発・普及活動など、自殺を考える人がいる限り、自殺と向き合う生き方を続けます。その決意ができた時にいつの間にか同志に出逢え、本当におかげさまで。。。。母の亡くなった年齢を超えることができて今も生き続けております。
今では「救えなかった」責任を感じて生きるというのではなく、「救える命」があることに気づかされたから、もう7歳ではない、もう少し長くなった現在の私の手足や心でやれることを、自らみんなとつながってやっていこうと歩んでおります。
ひとりぼっちと思わないで、自分から勇気を振り絞って、つながっていくことも大切なんだと感じています。
木下貴志さん
「近所に恥ずかしいから、こんなことはもうやめてくれ。」
この言葉は、母が自死未遂をした時に母に向かって吐き捨てた言葉です。
今となってはこの言葉が今の自分を苦しめ、取り返しのつかないことへ繋がるなんて思ってもみませんでした。
私の母親は11年前、自ら死を選びました。
父親との離婚、うつ病、仕事でのトラブル、そして孤立。自殺未遂。同居していた家の中では常に不安とやりきれない想いで精神的に不安定な母に冷たく当たっていました。当時「眠れない、仕事でミスをして怒られた、仕事へ行きたくない」と嘆く母親に対して私は、ただ理解できず、時にはひどい言葉を投げかけたり、突き放すような態度を取ったりしていました。次第に母親の行動が家族への大きな負担となり、いっそ家内や子供達を連れて別々に暮らしたいと思うほど厳しい状況になっていました。
そんな時、母親が自死未遂を起こし、母親に最初に言った言葉が冒頭の言葉でした。
自死をしようと行動を起こした母親の気持ちよりも、私自身や家内、子供の事が大切で、母親の行動に私自身迷惑をかけられたと思っていたのだと思います。酷い考えでした。
それから母親は数か月後の大晦日の日、家を出て、今度は本当に自死を選びました。
それから残された家族の苦しみが始まりました。
まさか本当に死を選ぶとは、私が殺してしまったようなものだ、どうして苦しみを理解してあげようとしなかったのか。すべては遅かった、母親に対し、とりかえしのつかない事をしてしまった自分を責めました。
近所や周りではすでにひそひそと立ち話をする姿、よそよそしい姿がありましたが、その事に私自身が一番嫌がっていたはずなのに、そんなことに対してはもうどうでもよくなっていました。
母親の今までの行動の中で、「何もしたくない、眠れない」と訴えていた時、どうして向かい合ってあげられなかったのか、ずるい考えをしているのではと何故突き放してしまったのか、どうして孤立させてしまったのか、きっと私のことを恨んでいるのに違いない、母親に会って話を聞きたい、謝りたいと何度も何度も考えました。
母親がいなくなってから常に襲ってくる自責の念に苛まれる自分と、突然静かな生活に戻った事へ安堵感を感じる自分への醜い罪悪感、残された家族の中での父親としての立場、家内、子供には辛い表情を見せまいと我を張る苦しさが入り混じり、誰にも相談出来ず、何とか自分を抑えることに必死になっていました。
それから家族の中では母親のことには一切触れることができない気まずい雰囲気での生活の中、母親の友人知人が訪ねて来ても「母親はここにはいません」と偽って答えたり、当時5歳や3歳だった子供達が私や家内に尋ねる祖母が家に居ない理由に対しても理解出来るように伝える事が出来なかったり、ただ年月が経っていくだけで、母親の自死のことに向かい合えない、避けようとしている自分に自問自答する日々、決して消えない繰り返し襲ってくる自責の念を抱えながらも生活をしている自分がいます。
11年経ち、分別の付く年齢になった子供達へ未だに祖母の事に向かい合って伝えることが出来てはいません。子供達もあえて祖母の事に触れようとしないのは、何か感じているのだと思います。
時代が変わり、身内から自死者を出してしまった残された家族への理解が、社会的にも地域的にも少しずつですが前に進み、自死に対して向かいあう為に遺族が集まる分かち合いの会や、行政側のサポート環境が整いつつあります。
このように自死者が増加している混沌とした時代の背景に、自殺によって辛い思いを抱えている残された自死遺族や友人、知人達がいる事に対し理解を深め、社会全体の問題として考えていただければと思います。
自死者を減らし、不幸にも自死者を出してしまった者への偏見をなくす社会になることを社会全体で取り組む事が必要だと思います。
(平成21年版内閣府発行自殺対策白書より)
*木下さんは、2008年9月に「浜松分かち合いの会」を立上げ活動しておられます。
浜松分かち合いの会
あの頃は本当に大変だったね。
でもこうやって二人で生きていられて幸せだね
田口まゆさん
私の住んでいた町は、過疎の町で、電車は通っておらず、唯一の交通機関はバス。それも1時間に1本しかありません・・・。
冬には雪が降ると町から出れなくなるような、そんな田舎の町です。
父が亡くなったのは、今から24年前、私が13歳の時でした。
小さな町だったので、父の自死はあっという間に町中に広まり、知らない人はいませんでした。
「隠す」ことなどもちろん出来ず、教師からの差別を受け、それでも母に心配をかけたくない一心で、中学高校と地元の学校に必死に通い、母一人子一人で肩身の狭い思いをしながらずっと生きてきました。
あの頃の私の心配事は、父を自死で亡くし、精神的にも肉体的にも弱った母でした。
母まで死んだらどうしよう、ということしか頭にありませんでした。
現在はおかげさまで、母も仕事を退職し、地元で穏やかに毎日を過ごしています。
長年父の自死のことは母との間でもタブーだったのですが、最近になってようやく二人で「あの頃は本当に大変だったね。でもこうやって二人で生きていられて幸せだね」と語ることが出来るようになりました。
父の自死の原因の本当のところは、もちろん父にしか分かりませんが、私が色々な人に聞いた話では・・・家族の借金問題でした。
父方の祖母が借金癖がある人で、父は祖母の代わりに近所の人に頭を下げて肩代わりしていたようでした。亡くなった時は父は貯金が全くない状態だったそうです。
父本人は派手な人ではなく、大変質素な生活をしていました。
母は父から祖母の借金の返済のことなど一切聞いていなかったそうです。
最近になり、父の自死後から半ば絶縁状態だった父方の親戚達との交流が再開しました。
先日も25回忌を無事親族一同で終えることができ、その時に更に色々な人たちから話を聞くことが出来ました。
長い間ずっと、私は自死した父だけが犠牲になったのだと思い、父方の親戚をひどく恨んでいたのですが、実は父以外の兄弟も祖母の借金問題で大変苦労したようでした。
「父だけじゃない、家族全体が苦しんでいたんだな」と思いました。
そして、私は父が39歳という若さで自死したので、「父に似ている自分も39歳で自死するのでは」、という恐怖を抱えてずっと生きていたのですが(私は現在36歳です)、父の兄弟に再会し、少しその恐怖が薄れました。
おじ達は、病気をしながらも70歳過ぎて今も懸命に生きている・・・
私にはこの人たちと同じ血も流れているんだ、と思うと「私もおじ達のように生きられるのでは」と感じたからです。
私の経験や感じたことが、もちろん自死遺族の方全てに当てはまるわけではありませんが、少しでも、自死遺族当事者の声を皆さんに聞いて頂きたくて、「自死者・自死遺族に対する差別偏見を失くす会」という会を立ち上げ、代表として活動をしています。
(ブログhttp://ameblo.jp/mira1105/)この活動を通じて少しでも多くの遺族の皆さんとつながることが出来たら嬉しいな、と思っております。
情報が欲しかった
柴原歩さん
大学に行きたかった。大学に行って心理学を勉強してカウンセラーになりたかったけど、でも大学に行けませんでした。16歳の時に父が自殺し借金の精算など資金面で苦しいという事でそれを言われたら何も反論はできない。それは仕方ないことだと思っていました。
数年を経てやりたい事も変化し、カウンセラーになりたい事など忘れ全く別の分野に進みつつも、父の死は私から離れる事はなくいつも身体のどこかで潜んでいて何かの拍子に顔を出して来ました。
この根源的な、永遠と続くであろう喪失感は突如溢れ出し自分で制御することなんてできないし、誰かに話して一時の助けになるけど一生救われるものではない。でもその喪失感を知っていると言うことで何か自分にもできる事があるのではないかと考えるようになりました。そんな矢先にライフリンクの1000人調査に参加する機会を得て参加しましました。2時間ほどお話を聴いていただき、話の中で年齢の話になり調査員の方へお歳をお伺いしたら私と同じ歳で同じ頃にお父様を自殺で亡くされたと話してくれました。ふと質問しました。
「大学、行かれたんですか?」
答えはイエスでした。
たまたま家のポストに入っていたあしなが育英会のパンフレットをお母様が渡してくれたとのことでした。
私はずっと大学に行けなかった理由は、父が自殺したから「だけ」ではなく、たまたま奨学金の事「知らなかった」という事実もあったということです。
すごく悔しかったです。私だって知ってたら大学行けて、本当に好きな事をできてたのに、と。この情報の格差をすごく憎みました。
でも何故かそこから自分のやりたい事が徐々に明確になり何が問題でどの問題に取り組みたいのか、分かったように思います。
結果として、私は大学に行けなかったんじゃなくて行かないことを選んで別の分野に進みましたし、あの時味わった情報の格差に対して、自分の選んだ分野で情報格差・自殺問題取り組む道を見つけることができました。
私は、もっと多くの人に、その時その人が求めている情報を届けたい。
最善の情報を多くの人に届けるのがそれが私の願いと使命です。